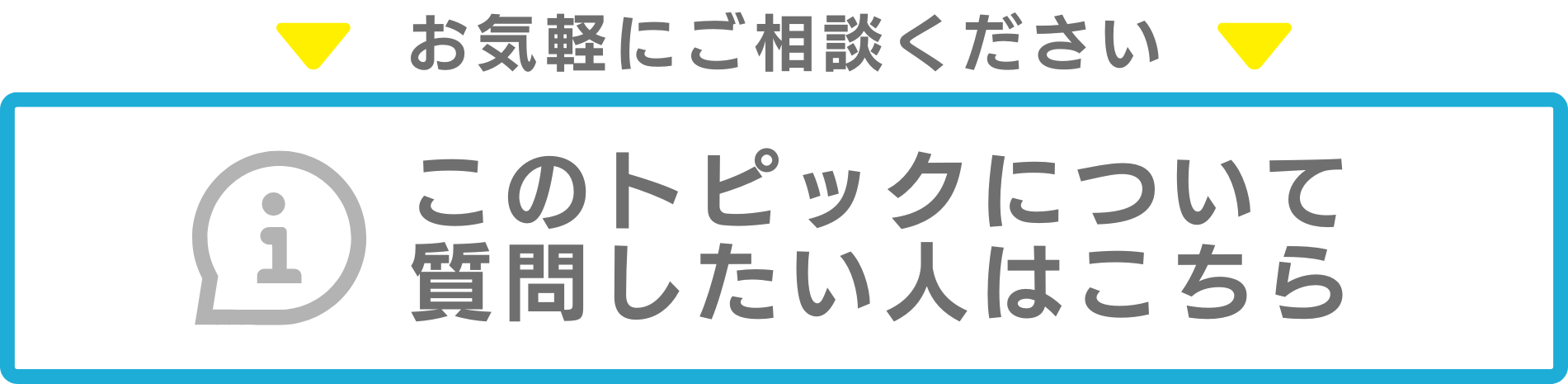「子どももいないので、遺産は慈善団体に寄付したい」
「お世話になった団体があるので、遺産はそちらに渡したい」
「家族との仲が良くないので、財産はほかの人に残したい」
このように考える人も少なくはないでしょう。
ここでは「遺産を寄付する方法」を紹介していきます。
なおあくまで主題は「寄付」ですから、「家族以外の特定の個人を指定し、その人に遺産を渡す方法」は原則として取り上げません。
配偶者や直系尊属・直系卑属がいても寄付はできるか?
「身内がまったくいない」という場合だけでなく、配偶者や直系尊属(父母や祖父母)・直系卑属(子どもや孫)がいる場合であっても、遺産を寄付することはできます。
ただし法定相続人がいる場合、彼らには遺留分を請求する権利があります。
配偶者や直系卑属の場合、2分の1を主張することができます。
直系尊属の場合、3分の1を主張することができます。
ただし、兄弟姉妹(直系卑属や父母がいない場合、法定相続人となりうる立場)の場合は遺留分を主張することはできません。
そのため、たとえ遺言書で「すべての遺産を、Aという団体に寄付する」と記してあったとしても、配偶者や直系卑属が遺留分を主張した場合は2分の1しか寄付することができません(直系尊属の場合は3分の1)。
もちろん「これが故人の意志ならば遺留分は主張しない」とする人も多いかと思われますが、この「遺留分」の考え方は念頭においておかなければなりません。
遺産を寄付する方法
遺産を寄付する方法には、遺贈・死因贈与の2つがあります。
遺贈について
「遺贈」の方は、イメージが付きやすいかと思われます。遺言書に記すもので、「財産の●割を、▽という団体に寄付する」などのようにします。
ちなみにこの「遺贈」には、「包括遺贈」と「特定遺贈」の2つがあります。包括遺贈の場合は、資産だけでなく負の財産(借金など)も一緒に引き継ぐことになります。対して特定遺贈の場合は、特定の財産のみを指定して渡すもので、負の遺産を引き継ぐことはありません。
なお遺贈を行う場合は、「残した財産は開発途上国の貧困をなくすためだけに使ってくれ」などのように、その使い道を指定することができます。これは「負担付遺贈」と呼ばれる行動です。もしこの「負担(条件)」をクリアしなかった場合、相続人がその負担(条件)を果たすように要求することができます。また、それでも履行されない場合は、遺言の取り消しを求める訴えを起こすこともできます。
死因贈与について
死因贈与は、遺贈と似て非なるものです。これは、「遺産を受け取らせたい団体に対して生前に『自分が死亡した場合は、あなた方に財産をお渡しする』と表明して、かつその団体がそれを了承した場合」にのみ成り立つものです。
遺贈との最大の違いは、「団体側の承諾があるかどうか」です。遺贈の場合は団体側が知らなくても成立しますが、死因贈与の場合は団体側と残す側で事前の合意―契約が必要なのです。
死因贈与の場合も、同じように条件を指定することが可能です。なおここでは「団体」をメインとして取り上げているため詳しくは記しませんが、死因贈与は「相続人として指定された側の権利を守ることができる」というメリットがあります。
たとえば、「介護をしたら財産を渡すと言われていて20年間も介護をしたのに、1日だけ旅行のために家を空けたら財産を渡さないと言われた」などのような状況になっても、相続人として指定された人間はきちんと財産を受け継ぐことができるわけです。
寄付したい場合は、やはりプロの元での遺言書の作成が望ましい
法定相続人がいてもいなくても、遺産を団体などに寄付することは可能です。ある程度大きい慈善団体の場合(例:ユニセフなど)では、「遺産寄付プログラム」としてページを設け、解説もしています。
ただ、「法定相続人以外に遺産を引き継がせたい」ということであれば、遺言書をしたためておく必要があるでしょう。またこの遺言書の作成にあたっては、プロの手を借りる方が安心です。遺言書自体は自分1人の力で作成できるものではありますが、遺言書は書き方が決まっているものでもあります。この書き方から逸脱した場合、遺言書が効力を発揮しないこともあります。このようなことになった場合、自分の遺志を尊重してもらえるかどうかは、法定相続人の判断にゆだねられてしまうことになります。
「絶対にこの団体に残したい」「たとえ遺留分を主張されることになったとしても、私自身の意志としてはあくまで『すべて寄付』だということを伝えたい」ということであれば、やはりプロの指導の下で遺言書を作る方がよいでしょう。
なお、「遺産を家族に渡したくはないが、どこの団体に寄付すればよいのかまだ迷っている」という場合は、団体の実態などを慎重に精査するようにしてください。