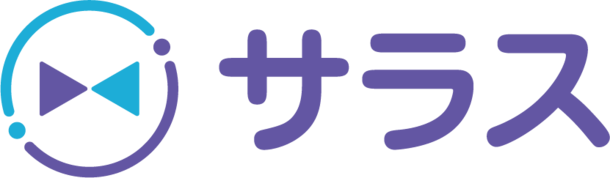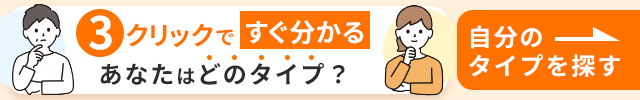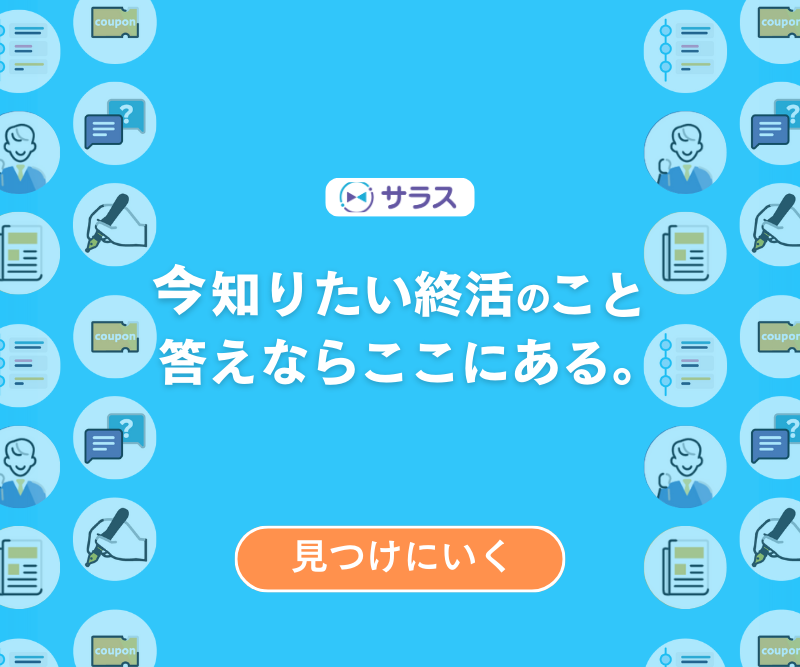贈与税法では、住宅取得等資金の贈与に関する非課税特例が設けられています。
これは、一定の条件を満たすと、住宅の取得や建築、リフォームに係る資金の贈与に贈与税がかからなくなるというものです。
この記事ではこの非課税特例の適用要件について詳しく説明していきます。
贈与の目的
非課税特例の適用を受けるためには、贈与の目的が住宅の取得、建築、リフォーム、または借地権の取得に限定されている必要があります。つまり、贈与された資金が住宅に関する目的に利用されることが求められるということです。
受贈者の適用要件
以下は国税庁のウェブサイトで公開されている受贈者の適用要件です。
(内容が分かりにくいものに解説をつけています。 )
1.贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(贈与者は受贈者の直系尊属)であること
– これは贈与者と受取人は、直系尊属または兄弟姉妹のいずれかの関係にある必要があります。直系尊属には、配偶者、子供、孫、親、祖父母などです。配偶者の父母、祖父母は直系尊属にはなりませんが、養子縁組をしている場合は直系尊属に該当します。この関係がない場合は、非課税特例の適用は受けられません。
2.贈与を受けた年の1月1日において、18歳以上であること
– 贈与を受けた年の1月1日において、18歳以上であること。受取人が満18歳未満である場合、または満18歳以上であっても学校教育のための贈与である場合は、非課税特例の適用を受けることができません。
3.贈与を受けた年の年分の所得税にかかる合計所得金額が2,000万円以下(新築等をする住宅用の家屋の床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の場合は、1,000万円以下)であること
4.平成21年分から令和3年分までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けたことがないこと(一定の場合を除く)
5.自己の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある人から住宅用の家屋の取得をしたものではないこと、またはこれらの方との請負契約等により新築もしくは増改築等をしたものではないこと
– この場合の取得というのは“購入“のことです。親族などの一定の特別な関係にある人から住宅用の家屋の購入をしていると適用要件から除外されてしまいます。そして、親族などの関係にあたる人が建築業者だった場合、そのお店を利用して増改築等をしていたらそれも除外されるということです。
6.贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること
(注)受贈者が「住宅用の家屋」を所有する(共有持分を有する場合も含まれます。)ことにならない場合は、この特例の適用を受けることはできません。
7.贈与を受けた時に日本国内に住所を有していること(受贈者が一時居住者であり、かつ、贈与者が外国人贈与者または非居住贈与者である場合を除く)
(注)なお、贈与を受けた時に日本国内に住所を有しない人であっても、一定の場合には、この特例の適用を受けることができます。
8.贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること、または同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること
(注)贈与を受けた年の翌年12月31日までにその家屋に居住していないときは、この特例の適用を受けることはできませんので、修正申告が必要となります。
出典:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
相続時精算金銭選択の特例
相続時精算金銭選択の特例とは住宅取得等資金の贈与を受けた場合に適用できる贈与税の特例の一つです。
相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産については、贈与者が亡くなった時点で相続財産に加算されます。また、贈与時に支払った贈与税額は、相続税の計算上、相続税額から控除されます。つまり、この特例を選択すると、一定の要件を満たした上で、将来の相続税額から既に支払った贈与税額を差し引くことができます。
住宅取得等資金についての注意点やポイント
特例の適用条件と非課税対象の金額
特例を受けるためには、贈与者の年齢が60歳以上、受贈者の年齢が18歳以上であること、贈与額が一定額以下であることなどの条件を満たす必要があります。条件を満たした場合、一定額以下の贈与については贈与税が課されません。
贈与財産の利用目的と申告手続き
特例の適用を受けるには、贈与された資金を住宅取得や建築、リフォームなどの特定の目的に利用する必要があります。また、贈与の際に必要な書類を適切に提出し、特例の申告と手続きを行わなければなりません。
相続時精算課税制度と相続税の関係
相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産については、贈与時に支払った贈与税額が相続税の計算上、相続税額から控除されます。
例外の適用には様々な条件や手続きがあるため、実際に適用する際には、税理士等の専門家に相談して、適切に対応を行えるよう対策することをおすすめします。