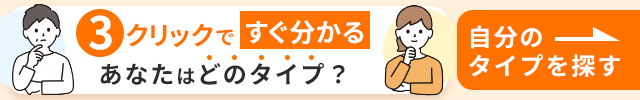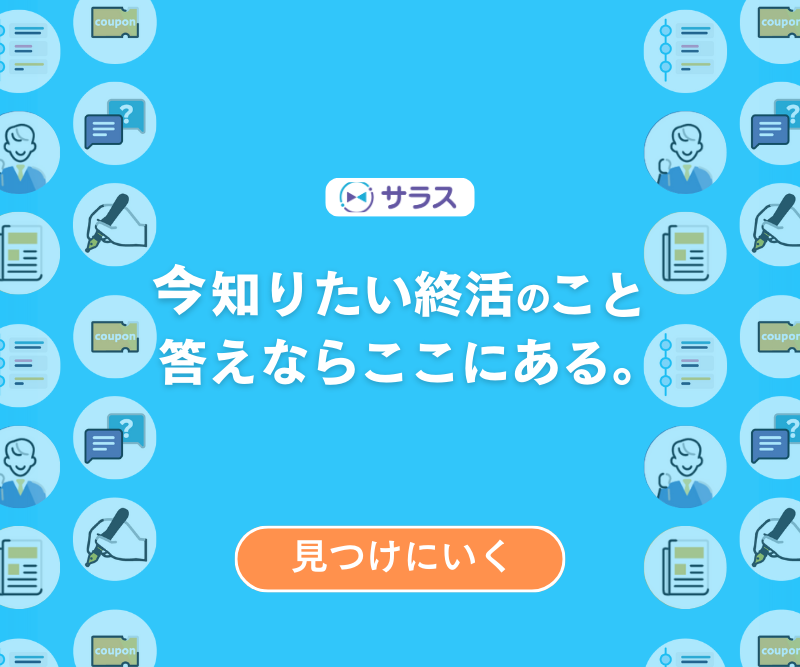「相続をすると、必ず相続税が発生する」「親から遺産を受け継ぐと、相続税を納めなければならない」と考えている人は、それほど少なくはありません。しかし実は、日本では「相続税の基礎控除」という考え方があるため、相続税が発生するケースは決して多くないといえます。
ここでは、
・法定相続人の基礎控除とは何か
・基礎控除の計算式
・法定相続人の数と考え方
について解説していきます。
法定相続人の基礎控除について説明
「相続税における基礎控除」とは、ごく簡単に言うのであれば、「引き継いだ遺産が、この金額以内に収まるのであれば、相続税は発生しません」という制度のことです。相続が発生した場合、受け継ぐ金額が下記の計算式を超えた場合は相続税が課せられます。しかしこれ以下で抑えられれば、相続税を支払う必要はありません。また、基礎控除を超えた場合も、課税対象となるのはあくまで「基礎控除を超えた分だけ」です。
相続税における基礎控除額の計算式は、以下の通りです。
“課税価格の合計額 - 基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)= 課税遺産総額”
ここで取り上げている「法定相続人」とは、「遺言書などがなかった場合に、法律に基づき、故人の遺産を引き継ぐことになる人」を指す言葉です。
配偶者は常に法定相続人となり、子どもがいれば子どもも法定相続人となります。また、「子どもが親に先立って亡くなってしまったが、その子どもの子(孫)がいる」という場合は孫が「代襲相続」というかたちで遺産を受け継ぐことになります。また、場合によっては親や兄弟などが法定相続人となることもあります(後述します)。
なお、「内縁の妻」などは法定相続人にはなりません。日本の場合は、「法定相続人であるかどうか」を決めるのはあくまで「戸籍」であって、生活実態は相続には影響を及ぼしません。
※上記の想定は、だれも法定相続人から廃除されなかった場合を想定しています。
相続税が発生しないケースが全体の9割を占める
なお、すでに述べた通り、「相続が発生した=相続税を納める必要がある」ではありません。実際に、相続税が発生する相続の割合は、相続全体に対して9.3パーセントと、1割以下にとどまっています。またこの「9.3パーセント」という数字は令和3年のものですが、平成24年~平成26年まではさらに課税対象となったケースが少なく、4.0パーセント~4.5パーセント程度で推移していました
相続税を払わなければならない割合は、多少の増減はあるものの、基本的には右肩上がりです。しかしこれも、被相続人の数もまた右肩上がりになっていっていることを考えれば、それほど不自然なものではないといえます。この「相続税を支払わなければならない人の割合」は、今後も急激に伸びる可能性はそれほど高くはないでしょう。相続税の計算や考え方は時代によって少しずつ変わっていっていますが、現在の制度がこのまま維持された場合、大半の人は相続時において相続税を支払う必要はないといえます。
なお、日本では「引き継ぐ財産が多ければ多いほど、相続税が高くなる」という制度が敷かれています。相続税の税率は10パーセント~55パーセントと段階的に分けられていて、引き継ぐ資産が大きくなれば大きくなるほど、支払う税金が高くなります。ちなみにもっとも相続税が高くなるのは、取得金額が6億円を超える場合です。
ただ、一般的な家庭で資産が6億円をおけるケースはまったくといっていいほどないでしょう。またこのようなレアケースにあてはまる場合、基本的には相応の節税対策が敷くために、税理士などに専門的な相談をすることになります。
なお、相続する金額が、基礎控除内に収まる場合は、申告自体が不要です。ただし、「本来は申告しなければならない状況であるにも関わらず、申告をしていなかった」という場合は、延滞税などが課せられます。延滞税などがついた場合、支払うべき相続税の金額は当然に通常のときよりも高くなります。また、相当に悪質だと判断された場合は、懲役刑が科せられることもあります。
このため、「本当に自分たちの相続では、相続税を納める必要がないか」はきちんと見極める必要があるといえるでしょう。
法定相続人の人数による控除等
上記では「基礎控除の計算式」について取り上げてきましたが、ここからはより具体的に「それでは、実際に相続が発生した場合はどれくらいの金額までなら基礎控除にあてはまるのか」を考えていきましょう。
配偶者がいて、配偶者との子どもが2人いる
配偶者も子どもも、当然に法定相続人と判断されます。そのため、基礎控除額は3000万円+600万円×3人=4800万円 となります。
配偶者と離婚済みで、子どもが2人いる。10年以上連れ添った内縁の妻がいる
離婚した元配偶者は、法定相続人にはなりません。子どもは法定相続人となります。上でも述べましたが、相続においては、「内縁の妻」などのような「戸籍のうえでは関係のない人」は原則として遺産の相続はできません。遺言書で内縁の妻に遺産を渡すように書き記すことはできますが、この場合も、「基礎控除」の人数には影響を及ぼしません。
そのため、基礎控除額は3000万円+600万円×子ども2人=4200万円 となります。
配偶者がいて、配偶者との間に子どもが2人いて、前妻との間に子どもが1人いる
現在の配偶者と、その間にできた子どもは、上記で解説した通り法定相続人となります。また、前妻との関係が切れていた場合であっても、故人と子どもの間の(相続上の)関係は維持されるため、前妻との子どももまた法定相続人となります。
そのため、基礎控除額は3000万円+600万円×4人=5400万円 となります。
配偶者がいて、配偶者との間に子どもが1人いて、養子にした子どもが1人いる
養子には「普通養子」と「特別養子」がありますが、どちらを選んだ場合でも、養親と養子の間には相続上の関係ができます。また、現行の日本の法律では、養子であっても実子であっても、受け継ぐ財産の割合に違いはみられません。
そのため、基礎控除額は3000万円+600万円×4人=5400万円 となります。
なお、普通養子縁組で養子となった子どもは、養親と実親、両方の法定相続人となります。対して特別養子縁組で養子となった子どもは、養親の法定相続人とはなりえますが、実親の法定相続人ではなくなります。
配偶者がいて、配偶者との間に子どもが2人いて、遺言書で別の子ども1人を認知した
遺言書の効力のひとつとして、「遺言認知」があります。これは、「遺言書でもって、子どもを自分の子どもとして認知する」というものです。この遺言認知によって認知された子どもも、故人の子どもとして扱われ、法定相続人として数えられます。
そのため、基礎控除額は3000万円+600万円×4人=5400万円 となります。
配偶者がいて、子どもがおらず、両親が健在である
子どもがいない夫婦の場合は、配偶者と、実親が法定相続人となります。
そのため、基礎控除額は3000万円+600万円×3人=4800万円 となります。
配偶者がおらず、子どももおらず、兄弟2人のみが存命である
配偶者もおらず子どももおらず、かつ両親もすでに他界済みである場合は、兄弟姉妹が相続人となります。そのため、基礎控除額は3000万円+600万円×2人=4200万円 となります。
また、このようなケースでさらに兄弟姉妹も他界していた場合は、兄弟姉妹の子ども(甥・姪)が代襲相続することになります。しかし甥・姪も他界済みの場合は、甥・姪に子どもがいても、その子どもは代襲相続することはできません。