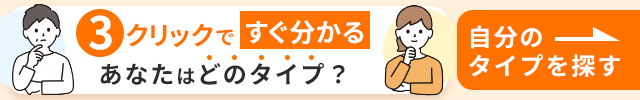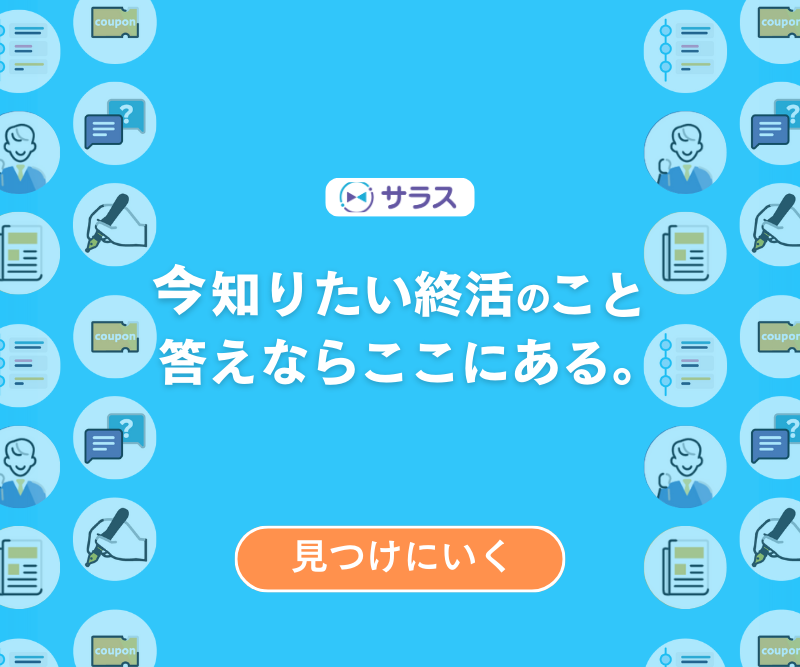「戸籍謄本」という言葉はだれもが一度は耳にしたことのある単語でしょう。
この戸籍謄本は、人が亡くなったときにも必要となるものです。
・戸籍謄本とは何か
・死後に戸籍謄本が必要になる理由とは
・どのようにして取得したらよいのか
について解説していきます。
戸籍謄本とはいったい何のこと?
「戸籍謄本(こせきとうほん)」という単語を耳にしたことのある人であっても、その詳しい内容まで説明ができるという人はそう多くはありません。
ここではまずは「戸籍謄本とは何か」について解説していきます。
戸籍謄本とは、「その戸籍に存在する人全員の個人情報(名前や生年月日、両親の名前や続柄)や、出生や婚姻について書かれたもの」をいいます。ちなみに非常によく似た性質を持つものとして「戸籍抄本(こせきしょうほん)がありますが、戸籍謄本がその戸籍に存在する人全員のデータを扱っているのに対し、戸籍抄本は個人1人だけの個人データを記載しているものであるという違いがあります。
なおここでは今もなお根強く使われている「戸籍謄本」という呼び方を使っていますが、実は平成16年から「戸籍全部事項証明書」という名称に変わっています。また、戸籍抄本も「戸籍個人事項証明書」と変更されています。
戸籍の歴史は非常に古く、日本最古の書物である日本書紀にはすでにこれの記載があります。
その後の歴史のなかでもこの戸籍の考え方は受け継がれていて、現在でも身分を表すための重要なデータとして取り扱われています。
死後に戸籍謄本が必要となるその理由は?
大切な家族が亡くなった後、この「戸籍謄本」は非常に大きな役割を果たします。
なぜなら戸籍謄本がないと、
・遺族年金を申請すること
・個人名義の銀行口座の名前を変えること
・不動産などの所有権を変えること
・相続税を申告すること
・葬祭料などを申請すること
などができなくなるからです。これらは「金銭」「相続財産」に直結するものであるため、非常に重要です。
そもそも、戸籍謄本がなければ、「相続人はだれであるか」の確証が持てなくなってしまいます。
「相続人って、つまりは自分の兄弟姉妹や親のことでしょう? さすがにそれくらいは全員分かる」という人もいるかもしれません。
しかし実際に、「実は自分(故人の子ども)は知らなかったけれど、亡くなった親には自分の知らない子どもがいた。父親違いの兄弟姉妹がいたことを、母親の死後に戸籍謄本を取り寄せて初めて知った」というケースもあります。
親戚縁者と密な付き合いを続けていたり、生前に親から打ち明けられた人が存命であったりする場合は、このようなケースでも「会ったこともなければ、見たこともない兄弟姉妹」と連絡を取れることもあるでしょう。
しかし戸籍謄本で死後になって初めてこのような事実を知った場合、混乱に陥ることは必至です。ただそれでも、相続に関しては「相続人全員で分割して行うこと」が原則です。相手の住所がわからない場合は、「戸籍の附表」をたどったり、遺産分割調停を検討したりしなければなりません。これを行わなければ、大きなトラブルになります。
逆に言えば、このような「後々に起きるかもしれない大きなトラブル」を避けるためにも、戸籍謄本を取ることは必要だということです。
戸籍謄本の取り方
戸籍謄本は、故人の直系の血族あるいは配偶者であれば取ることができます。
この際には、
・相続する人の本人確認証明書類(パスポートや運転免許証など)
・印鑑
の2つが必要です。また代理人に取ってもらうときは、これに加えて委任状が必要となります。
戸籍謄本は郵送でも取得することができますが、この場合手続きが煩雑になったり返信用封筒が必要になったりします。
人が亡くなった場合はどれほど遠方に住んでいたとしても、非常に少ない特例を除き必ず一度は故人の戸籍がある住所に戻る可能性が高いため、このときに手続きをしてしまうとよいでしょう。
ちなみに、かつては複数の戸籍謄本が必要でした。
しかし平成29年に「法廷相続証明情報制度」が始まりました。この制度の施行は非常に画期的で、謄本一式を法務局に提出しさえすれば各機関への提出が必要な書類を受け取ることができるようになりました。
これを使うことで、非常に簡単に手続きができるのです。
なお、戸籍謄本関係に限らず、人が亡くなった後の手続きは非常に煩雑です。特に「お金」が絡むものの場合、事態は複雑化します。状況によっては、人間関係がこじれる可能性もゼロではありません。
そのため、「自分の手には負えそうもない」「非常に忙しいので、お金を払ってでもだれかに代行してもらいたい」「おそらくもめることになるかと思うので、第三者の視点と専門家の知識を借りたい」ということであれば、税理士や弁護士などの力を借りるとよいでしょう。