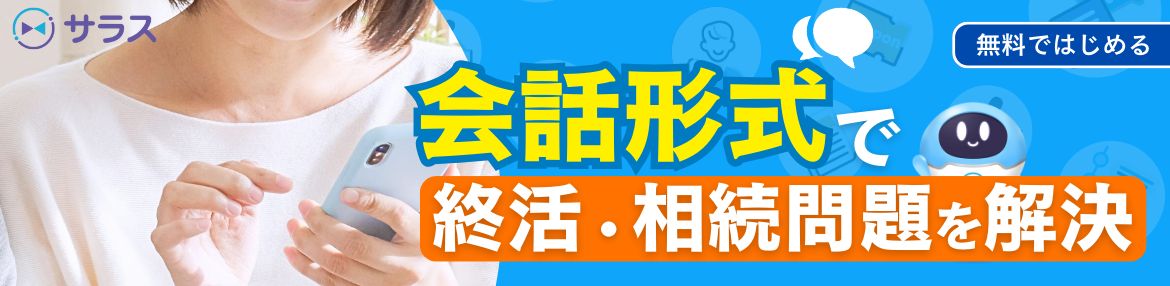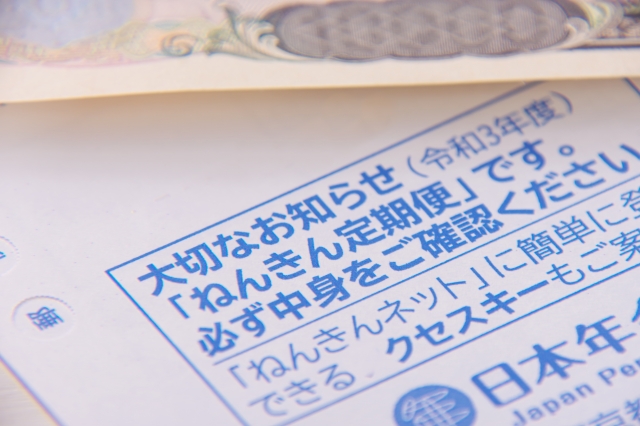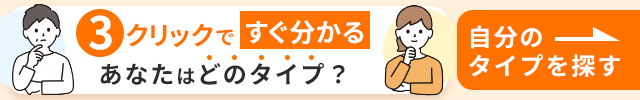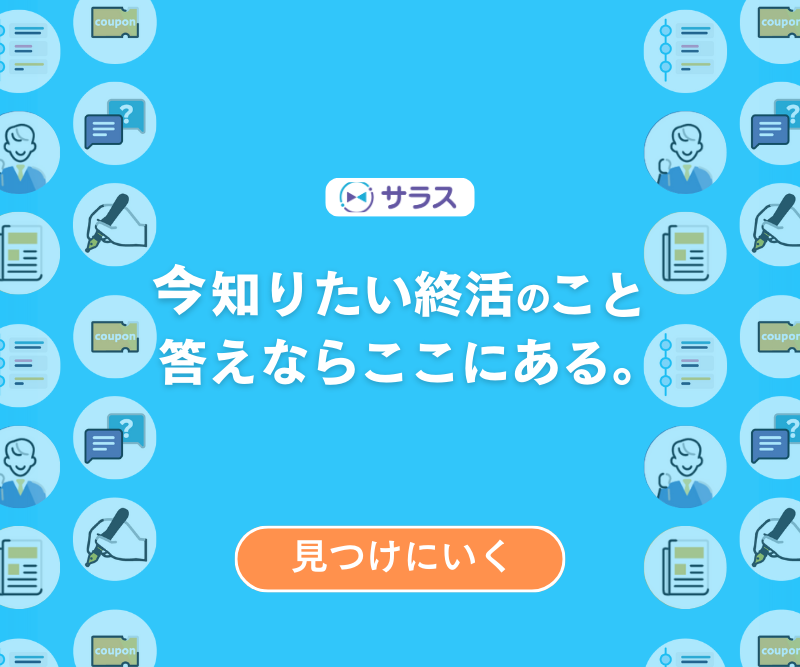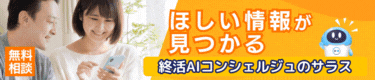故人の国民年金の受給停止は死後10日、厚生年金は14日が期日です。窓口は年金事務所または年金相談センターです。あわせて未支給年金や遺族年金の申請方法も紹介します。この記事は「故人の国民・厚生年金の手続きが知りたい」と悩む方に向けた内容です。
【この記事の要約】
・故人の国民年金の受給停止は死後10日、厚生年金は14日が期日
・手続きは年金受給権者死亡届と年金証書、死亡診断書のコピーを年金事務所へ持参する
・国民・厚生年金の手続き時に条件を満たせば未支給年金や遺族年金の受給も可能
・遺族間トラブルや法律に関する悩みは専門家の弁護士へ相談する選択肢もある
国民・厚生年金の受給停止の手続きは死後10日が期日
故人の国民・厚生年金の受給停止の手続きは、年金事務所または年金相談センターへ、次に添付する「年金受給権者死亡届」の提出をもって完了します。
参照:年金を受けている方が亡くなったとき|日本年金機構 (nenkin.go.jp)
・故人が国民年金加入者の場合、死後10日以内
・故人が厚生年金加入者の場合、死後14日以内
期日後に受給した国民・厚生年金は不正受給となるため返金が必要です。
国民・厚生年金の受給停止に手続きに必要な書類は3点
・年金受給権者死亡届
・故人の年金証書
・故人が死亡した事実がわかる書類
故人が死亡した事実がわかる書類は戸籍抄本や死亡診断書のコピー、もくしは死亡届の記載事項証明書を提示してください。
国民・厚生年金の受給停止の手続きは郵送も可能
年金事務所や年金相談センターが遠方である、または事情があり足を運べない場合は郵送での手続きも可能です。
郵送での年金受給停止の手続きを希望の方は基礎年金番号を確認のうえ「ねんきんダイヤル」0570-05-1165までお問い合わせください。
出典:電話での年金相談窓口|日本年金機構 (nenkin.go.jp)
未支給年金は故人の死後5年以内の手続きで受け取り可能
年金は偶数月の15日に先月と先々月の2カ月分が支給されるシステムなので未支給年金(故人に払うべき年金)が発生します。
未支給年金を受け取り希望の方は国民・厚生年金の受給停止の手続きの際に、次に添付する「未支給【年金・保険給付】請求書」もダウンロードしてご利用ください。
参照:nenkin-seikyu.pdf (kouekisya.com)
未支給年金は年金事務所、年金相談センターへ訪問もしくは郵送でのお手続きも可能です。郵送をご希望の方は「ねんきんダイヤル」までお問い合わせください。
未支給年金の受給条件は故人と生計を同一にする配偶者と3親等以内の親族
故人の収入で生活していた配偶者や住所は異なるが仕送りを受けていた3親等以内の親族であれば未支給年を受け取れます。
未支給年金を受け取れる優先順位は次のとおりです。
配偶者は親等に含まれません。
1親等:故人の子・両親・子の配偶者
2親等:故人の孫・祖父母・兄弟姉妹・孫の配偶者・兄弟姉妹の配偶者
3親等:故人からみた「ひ孫」・「ひ祖父母」・おじ叔母・おじ叔母の配偶者
未支給年金の受給に必要な書類は4点
・故人の年金証書
・故人と請求者の続柄を証明できる戸籍謄本や法定相続情報一覧図
・故人と請求者が生計を同じくしていたとわかる世帯全員の住民票
・未支給年金の受け取り口座情報
故人と請求者が別世帯にお住まいの場合は次に添付する「生計同一関係に関する申立書」の提出が必要です。
遺族基礎・厚生年金の手続きで生活をサポート
遺族基礎・厚生年金は、故人に生計を維持されていた方が受け取れる年金です。
故人の年金の納付状況や故人との関係性など条件を満たせば受給できます。
遺族基礎年金の受給要件4点と受給額
遺族基礎年金は、故人が次の4つのいずれかを満たしていれば「子のある配偶者」または「子」が受給できます。
・国民年金の被保険者である間に死亡した場合
・国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有している方が死亡した場合
・老齢年金の受給権者であった方が死亡した場合
・老年基礎年金の受給資格を満たした方が死亡した場合
遺族基礎年金の「子」とは、婚姻していない18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障がい年金の障がい等級1もしくは2級の方です。
遺族基礎年金の受給額は令和4年4月分から改正され、次の基準となりました。
・子の受給額は「777,800円+2人目以降の子の加算額」
・子のある配偶者の受給額は「778,000円+子の加算額」
子の加算額は1人目と2人目は各223,800円で3人目憩いは各74,600円です。
遺族年金の該当条件や受給額に関する不明点は日本年金機構までお問い合わせください。
参照:遺族基礎年金を受けられるとき|日本年金機構 (nenkin.go.jp)
遺族厚生年金の受給要件5点と受給額
遺族厚生年金は故人が次の5つの条件いずれかを満たせば「故人の遺族」が受給できます。
・厚生年金の被保険者である間に死亡した場合
・厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気や怪我で初診日から5年以内に死亡した場合
・1、2級の障がい厚生年金の受給者が死亡した場合
・老齢厚生年金の受給権者が死亡した場合
・老齢厚生年金の受給資格を満たした方が死亡した場合
遺族厚生年金の受給額は、故人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額です。
報酬比例部分は「平均標準報酬月額×一定乗数×加入期間」で計算し、平成15年3月以前と以後で分けて計算します。
平成15年3月までの平均標準報酬月額は、平成15年3月以前の各月の標準報酬月額の総額を、平成15年3月以前の加入期間で割って得た額です。
平成15年4月以降の平均標準報酬額は、平成15年4月以降の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、平成15年4月以降の加入期間で割って得た額を示します。
報酬比例部分の一定乗数は次のとおりです。
・平成15年3月まで「1000分の7.125」
・平成15年4月以降「1000分の5.481」
平成15年3月までの報酬比例部分と4月以降の報酬比例部分を足した額の4分の3が遺族厚生年金の受給額です。
遺族厚生年金に関するお問い合わせ先は日本年金機構です。
葬儀後の各種手続きは専門家の弁護士に相談する選択肢もある
故人の葬儀後は、国民・厚生年金の手続き以外にも遺産の相続や遺族間の話し合いなどやることが多いです。
心身共に疲れている時に、追い討ちをかけるかのように遺族間で相続トラブルが起こることも珍しくありません。
相続や法律トラブルでお悩みの際は1人で抱え込まず、専門家である弁護士へ相談する選択も有効です。
まとめ
国民・厚生年金の受給停止の手続きは故人が国民年金加入なら14日、厚生年金加入なら10日が期日です。
条件を満たせば、故人の未支給年金や遺族年金も受給できるので申請しましょう。
故人の相続トラブルや法律に関するお問い合わせは専門家の弁護士へご相談ください。