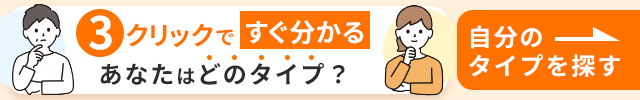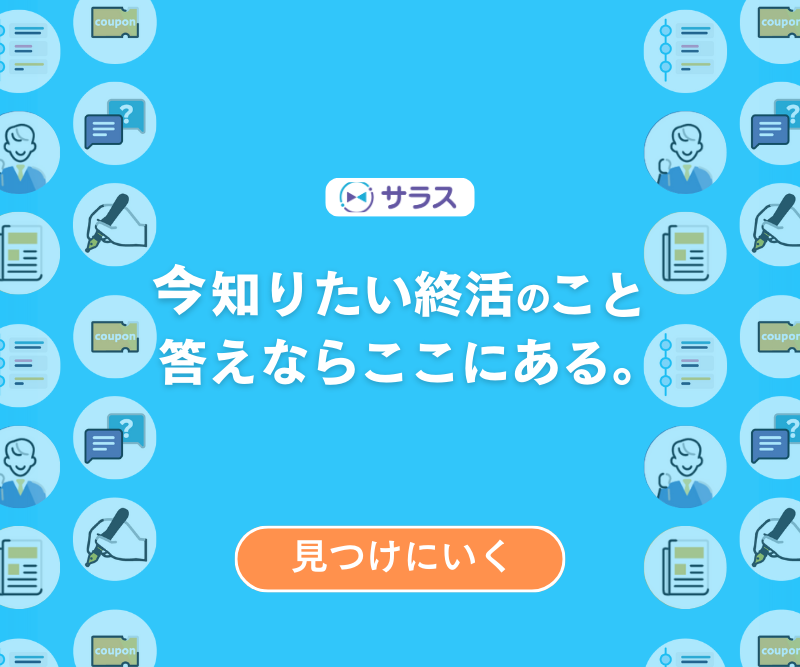令和5年度の税制改革は、相続税や贈与税の分野にも及んでいます。ここでは、令和5年度の相続税・贈与税の見直しの内容について解説していきます。
なお、令和5年度の税制改革は、令和6年の1月1日より施行されます。
※実際に対象となる人は、それを行う前に必ず最新の情報にあたってください。
※本原稿は、令和5年の7月末日に記しています。
相続時精算課税制度の見直し
「相続時精算課税の見直し」について知る前に、まずは「そもそも相続時精算課税とは何か」から知らなければなりません。
相続時精算課税制度とは、「財産をもらう側(=受贈者側)の受け取るお金の累計が2500万円未満であるのなら、贈与税を支払うことなくそれを受け継げる」という制度です。ただしこれを受けた場合、「財産を渡した側(=贈与者)」が亡くなった場合、相続時精算課税によって受け取ったお金の額と、贈与者が亡くなったときに引き継ぐことになった相続財産を合わせた金額から相続税が計算されます。
たとえば、父親が生きているときに、相続時精算課税制度を利用して1500万円の贈与を受け取ったとします。このときには、贈与税を納める必要はありません。
その5年後に父親が他界して、改めて相続財産として3000万円を受け取ったとします。このときになって初めて、1500万円+3000万円=4500万円分にかかる相続税が発生するというわけです。
ただし、もともと相続に関しては「基礎控除」という考え方があります。基礎控除額は、「3000万円+相続人の数×600万円」で求められます。仮に父親の相続人が子1人であった場合、もともと3600万円までは(相続時精算課税を使っていようが使っていなかろうが)相続税の課税対象外とはなりません。これが相続時精算課税制度の原則です。
これに加えて、令和5年度の税制改革では、「年間で110万円までの基礎控除が受けられる」となりました。
これは、「年間で110万円までの贈与であるのなら、相続財産の換算にも含めない(し相続税の対象ともならない)」とする制度です。
これによって、たとえば「(贈与税のかからない)2500万円まで贈与したとしても、それ以降の年でも110万円までは贈与税なしで贈与することができる」ということが可能になりました。
生前贈与の加算期間が延長
「生前贈与」とは、「自分が生きている間に、他者に対して財産を渡す制度」のことをいいます。これは、基本的には60歳以上の直系尊属が18歳以上の直系卑属に対して行うものであり、上記の「相続時精算課税制度」もこれに含まれます。また、もう「暦年課税(暦年贈与)制度」と呼ばれるものも生前贈与の一種です。これは「1年間に110万円までならば、税務署への申告不要で譲り渡しができる」という制度です。それ以外にも、次の項目で示す「教育資金贈与」などもまた、生前贈与のうちの一種です。
「相続する財産が多くなりそう」と予想される場合は、事前にこの生前贈与を行うことで、相続時に発生する相続税を抑えることができました。
今回紹介する「生前贈与の加算期間の延長」は、生前贈与の形態のひとつである「暦年課税」と深く関わるものです。
暦年課税制度には期間の縛りがありました。令和4年までの場合は、「死亡する3年前より後に生前贈与された財産については、相続税の対象とする」とされていました。
たとえば、「2000年から2019年にかけて、年間100万円ずつ子どもに生前贈与をしていたが、2019年の2月2日に亡くなった」という場合、亡くなる3年前までに(2016年の2月2日~2019年の2月2日まで)受けた生前贈与の分は、相続税の課税対象になるということです。
しかし今回の令和5年度の改正では、この期間がさらに延ばされて「7年」とされました。もともと、「亡くなる3年前にさかのぼって、生前贈与で受け継がせた財産を相続税の課税対象とする」という制度は、悪質な相続税逃れを抑制するためのものでした。
しかし今回それが7年へと延ばされたことの背景には、「より若い世代に財産を移すように促し、経済を活性化させよう」という狙いがあったものとみられています。
つまり、相続税対策として生前贈与を考えているのであれば、令和4年度よりも難しくなってしまったわけです。このため、積極的に生前贈与を行い相続税の課税対象財産を少なくしたいと考えるのであれば、早め早めに生前贈与を行っていった方が良いということになります。
教育資金一括贈与の非課税措置の見直し
上記でも述べたように、生前贈与のかたちのひととつとして、「教育資金贈与」があります。
これは、「30歳未満の直系卑属に対して、教育資金として一括贈与ができる制度」のことをいいます。この教育資金一括贈与のかたちをとるとき、1500万円までは一括で、それも非課税で、財産を渡すことができます。ただしこの教育資金一括贈与の場合は、受贈者の去年の合計所得額が1000万円以下であることも条件のひとつとされています。これが教育資金一括贈与の原則です。
ただ、令和5年の改訂では、この教育資金一括贈与制度に見直しが行われました。
教育資金一括贈与で渡された財産は、受贈者がそれを使い切る前に贈与者が亡くなった場合、使い切れなかった金額には従来通りの相続税が課せられるのが原則です。ただし令和5年よりも前の法律では、「受贈者が22歳以下であり、学校などの教育機関に在籍している場合は、相続税の支払いを免除する」とされていました。
しかし令和5年以降では、教育資金一括贈与の形式にのっとり、上記の「支払い免除」にあたるような形式であっても、「相続税が一定額を超える場合は、相続税課税の対象とする」とされました。
もっともこの「一定額」は5億円とされているため、このケースに該当するご家庭はそれほど多くはないと思われます。
また、教育資金一括贈与は「30歳未満の直系卑属に対して行えるものであり、教育資金としての性質を持つもの」という特徴があります。そのため、「若いときに教育資金一括贈与を受けたが、30歳を超えてもなお、そのときに受けた教育資金が残っている」という場合は残っている金額に対して贈与税が課せられていました。そしてこの贈与税の比率は、年齢によって決められていました。
しかし令和5年の改正で、「年齢に関わらず一定の税率とすること」が定められました。
結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置の見直し
教育資金の生前贈与の優遇の特例措置が取られているように、結婚・子育てに関しても一定額までを非課税にするという制度があります。それが「結婚・子育て資金の一括贈与の特例制度」です。
この結婚・子育て資金の一括贈与の限度額は、総額1000万円と定められています。なお不妊治療などの場合はそれだけで上限額の1000万円までの贈与を受けられますが、挙式などのみを目的とする場合は300万円を上限としています。
また、「結婚・子育て資金の一括贈与を受けたが、贈与者が亡くなった。そして残高が残った」という場合は、教育資金の贈与と同じように、この残高が相続税の対象となりました。
なおこの制度は本来は令和3年までの特例制度でしたが、今回の「見直し」によって、令和7年までの間継続されることになりました。
また、令和5年の改訂によって、「受贈者が50歳になったときに余っていた金額に対しては、贈与者が亡くなった時点で贈与税の対象とする」と定められました。
相続や贈与に関する法律は、細かな見直しが行われています。実際に贈与などを行う場合は、必ず最新の情報にあたるようにしてください。