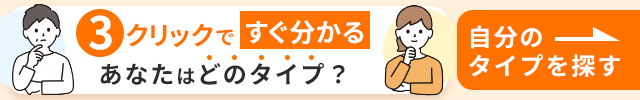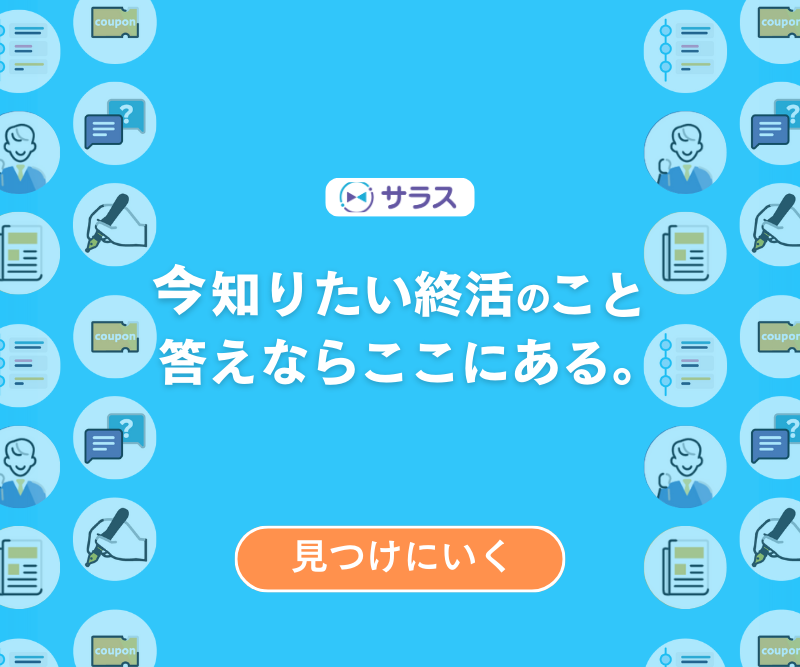人に財産を渡す方法は、いくつかあります。今回はそのなかから「暦年課税」と「相続時財産課税」を取り上げてその違いを解説しつつ、「贈与税がかからないケースとしてどのようなやり方があるのか」について解説していきます。
暦年課税と、相続時精算課税について知っておきたい
贈与税を考えるうえで、必ずピックアップされるのが「暦年課税(暦年贈与)」と「相続時精算課税」です。
この2つの特徴を見ていきましょう。
暦年課税
ある1人の人が受け取った1年間の財産に対して、贈与税が科せられる仕組みのことです。財産を渡す側と財産を受け取る側、両方とも立場に制限はなく、まったくの他人であっても受けられます(ただし、「特例贈与」を使う場合は、成人が対象となります)。
「年間の合計金額が110万円以下であるのなら、課税対象にはならない」とされているのが最大の特徴です。なお、110万円を出た分に関しては税金がかけられます。
ちなみに暦年贈与はだれに対しても行えるものです。まったく血のつながりのない人に財産を渡すことができる制度であるとともに、相続権を持っている人に対しても選択できる制度です。そのため、相続権のある人に財産を受け継ぐ場合は、「暦年贈与か、それとも相続時精算課税か」を選ぶことになります。
相続時精算課税
まず相続時精算課税制度と暦年課税制度では、財産を渡せる相手が異なります。相続時精算課税制度は「60歳以上の人が、18歳以上(※法律改正前は20歳)以上の人に渡せるものであり、渡される側は渡す側にとって直系卑属(孫や子ども)」でなければなりません。暦年課税方式での贈与は、相手を限定していませんが、相続時精算課税の方法の場合は制限があるのです。
また、相続時精算課税では、「贈与の額が総額で2,500万円を超えた場合、その超過金額に対して課税される」という特徴があります。ただ、2023年に相続時精算課税の見直しが行われて、相続時精算課税制度を利用した場合もまた、年間で110万円までの控除を受けられるようになりました。
贈与の方法と対策
暦年課税(暦年贈与)を利用して財産を渡す場合、たとえ何年間にわたって財産を渡し続けても、その額が110万円以下であるのなら課税対象とはなりません。
対して相続時精算課税の場合、「2,500万円までは課税対象とならず、年間110万円以下であるのなら課税対象とならない」ということから、「結婚式の費用として500万円を渡し、それ以降は110万円ずつ渡していく」という方法も可能です。
「子どもが18歳の時からコツコツと資産を移動をさせていきたい」という場合は、子どもが18歳のころから暦年贈与を始めるとよいでしょう。親が50歳であると仮定した場合、平均寿命である84歳までの間に、34年間で3740万円を渡すことができます。
相続時精算課税の場合は、「子どもが25歳で結婚式をして、500万円を渡す。残りの2,000万円を、18年間にわたって渡す」というやり方を取ることができます。
なお、一度でも相続時精算課税制度を利用した場合、暦年課税方式に切り変えることはできません。
暦年課税方式と相続時精算課税方式は、「財産の生前移動」を考えたとき、必ず出てくるキーワードです。どちらが良い・どちらが悪いと言えるものではありませんから、自分たちのライフスタイルに合わせた方式を選んで行くとよいでしょう。
最後に補足として述べておくと、遺言書がない限り、残した財産はすべて法定相続人にわたります。妻1人子ども2人の場合は、妻が2分の1、子どもが4分の1ずつ引き継ぐことになります。「ほかの人に財産を譲る」とする遺言書があったとしても、妻には4分の1の財産が残され、子どもには8分の1ずつの財産が残ります。
「今現在手元にある財産が1,000万円である。そのすべてを、赤の他人に渡したい」と考える場合は、暦年贈与を選んで10年間にわたってその人に財産を渡す…というやり方をとることを選択肢にいれるとよいでしょう。
贈与税がかからない場合
上記では、暦年課税方式と相続時精算課税方式を紹介しました。しか、条件は限定的ではあるものの、ほかにも贈与税がかからないケースもあります。
それについて見ていきましょう。
・法人からの贈与。
・公益性を目的とする事業の財産
・贈与税がかからない財産
・例外事項
ひとつずつ解説していきます。
法人からの贈与
法人格から財産を受け取った場合、贈与税はかかりません。これは、「贈与税」というものがそもそも、「いち個人からいち個人へ財産を渡すときに発生するものである」という考え方があるからです。ただ、「それならば会社を立ちあげて、そこの資産を全部渡してしまえば、税金を一切納めることなく資産を渡せるかというと、もちろんそんなことはありません。なぜなら法人からの財産の譲渡は、「所得税」というかたちで税金を徴収されるからです。
公益性を目的とする事業の財産
「亡くなった人が宗教法人を営んでいた」「慈善活動にお金を使っていた」などの人が、それに絡んだ財産を残したとします。残していった財産が、それらの運用に使われる場合は、贈与税が発生しません。
贈与税がかからない財産
残された子どもなどが、生活費や教育費にあてると考えられている財産には、贈与税はかかりません。なお、教育費用や治療費、子どもを育てるために必要な養育費なども、贈与税の対象外とされます。
ただしこれらはあくまで「残された家族の生活を守るためのものである」という考え方に基づくものです。そのため、「子どもの教育費用を賄うために株を買い、投資を行った。その結果、多額のお金が得られた」などのように、違う方法を経由してしまうと、贈与税が課せられてしまう可能性があります。
例外事項
これ以外にも、「結婚や子育てのため、直系損族(親や祖父母)から、直系卑属(子どもや孫)が受け取ったお金」は課税対象外とされることが多いといえます。また、「家を買うため」「教育費とするため」などの場合も、贈与税の対象外と判断される可能性があります。
ちなみに、人の好意として受け取ることになる「不祝儀」「花代」「お盆や年末年始のお中元やお歳暮として受け取ったもの」「お見舞い中に受け取ったお金」などは、一般的かつ社会通念から逸脱しない程度のものであると判断されるものならば、贈与税の対象とはなりません。
ここではいくつかの特例について話していきましたが、「特定障害者であり、特定の条件を満たす場合は、最大で6,000万円まで金額については贈与税がかからない」などのような特例があります。
障害を抱えている人が残される場合 あるいは障害を持っている人を抱えるご家族の場合には、給付面などでも少し違いが出てきます。そのためこのケースに該当する場合は、早めにきちんと調べておく必要があるでしょう。大切な人を亡くした直後に、このようなことを考えるのは大変なものですし、先に挙げた「暦年課税制度」「相続時精算課税制度」のように、生前から対応することを前提としている財産の動かし方も多いからです。
また、実際の資産運用については、専門家の見解を聞くのがもっとも正確です。なおその際に、「自分はこのようなかたちで財産を渡したい」「私はこのようなかたちで財産を受け取りたい」などのような希望がある場合は、それをしっかりと伝えておくとよいでしょう。
※数字や情報、そのほかの記載は、すべて2023年12月上旬の情報に従って作成されたものです。税制面での改革はしばしば行われているため、情報が古くなる可能性もあります。実際に財産を渡す・渡される、の立場になった場合は、必ず現行法を確かめ、必要に応じて専門家の意見を仰ぎつつ、慎重に資産運用を考えていってください。
出典:国税庁「No.4405 贈与税がかからない場合」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm