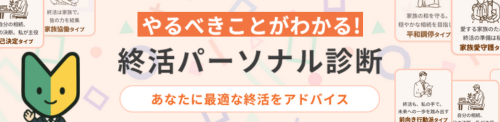「親や兄弟に遺産を渡したくない」と考える人は、決して少なくはありません。
ここでは、「自分のパートナーが上記のような考えを持っていた場合、配偶者として提案できる方法は何か?」に注目して解説していきます。
※ここでは、「夫=年齢的に老境に差し掛かっていたり、病気を患ったりしていて、遺産のことを考えている人」「妻=上記のような配偶者を持っている人」の想定で解説していきます。
相続の基本
まず、相続の基本に関して簡単に解説します。
遺産の行方を指定しなかった場合、
・配偶者
・直系卑属(子どもや孫)
・直系尊属(父母や祖父母)
・兄弟姉妹
が法定相続人となります。
「どれくらいの遺産を引き継げるか」は、立場や家族構成によって異なります。
たとえば、「配偶者と子ども1人がいる」という場合は、配偶者が2分の1、子どもが2分の1を受け継ぐことになります。「配偶者と祖母がいる」という場合は、配偶者が3分の2を、祖母が3分の1を受け継ぎます。「配偶者と兄弟姉妹が1人いる」という場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1を受け継ぐことになります。
これが相続の基本です。
これを踏まえたうえで、「妻以外の家族には遺産を渡したくないと夫が希望している」といったケースに寄り添っていきます。
遺産を妻以外に渡したくない!方法その1~遺贈などを利用する
「自分たちが結婚するときに、夫の親に反対されたすえに勘当同然の扱いをされた」
「兄弟姉妹からマルチ講に勧誘されたことがきっかけで、夫は兄弟姉妹と絶縁状態になった」
「親も兄弟姉妹も他界していて、私と夫と子どもだけで生活をしていたが、子どもが家庭内暴力をふるっていた時期があった」
などのような理由で、「妻以外の人に遺産を渡したくない」と希望する夫もいるでしょう。
その場合の対処方法となるのが、「遺贈などを利用する方法」です。
遺言書に、「すべての財産を妻1人に渡す」と記すのです。このようなやり方をした場合、法定相続人全員の合意が得られれば、妻1人が財産を受け取ることができます。
しかし相続には「遺留分」という考え方があります。これは法定相続人に認められている権利であり、「たとえ遺産の行く末を夫が決めていたとしても、法律で定められた一定の割合の財産の相続権を法定相続人は主張できる」というものです。
この遺留分に関しては、2段階のステップで計算します。
まず、「遺留分の合計はどれくらいか」を求め、その後でそれぞれの立場に認められた遺留分をかけあわせて計算します。
たとえば「配偶者と親がいる」という場合は、遺留分の合計は2分の1となります。
そして「それぞれの立場で認められる遺留分」は、直系尊属は3分の1、配偶者や直系卑属は2分の1と決められています。なお兄弟姉妹に遺留分は認められていません。
3億円×2分の1(遺留分の合計の割合)×3分の1(それぞれの立場で認められる遺留分)=5000万円 となります。
つまり、「3億円の遺産があり、妻にすべてを渡したい。しかし父親が存命中である。なお子どもはいない」となった場合、父親が受け取れる遺留分は、
遺言書などで「妻にしか渡さない」と指定するのは非常に一般的なやり方ではありますが、この「遺留分」が出てくるため、すべての財産を妻にのみ渡すことができない(できにくい)というデメリットがあります。
遺産を妻以外に渡したくない!方法その2~相続人廃除する
相続人を排除して、妻以外に相続をさせなくする方法もあります。これは遺留分さえも認めさせないやり方であるため、非常に強力です。
ただしこれが認められるのは、
1.夫に対して著しい侮辱行為を行ったり、虐待をしたりしたと認められた場合
2.顕著な非行行為が認められた場合
のみです。
たとえば「日常的に罵詈雑言を夫に対して吐いていた」「夫の名前を使って勝手に多額の借財を作った」などのようなケースです。「30年前に1度だけ、結婚を認めないと言われた」などのようなケースでは相続人廃除は認められないと考えられます。
また、これを行う場合は、生前に家庭裁判所に申し立てを行ったり、死後に遺言執行者によって申請を行ったりする必要があります。
「家族」の立場である妻が念頭に置いておかなければならないこととして、「廃除の申し立てを行えるのは本人だけである」という点が挙げられます。「夫の調子が悪いので、妻である私が代わりに相続廃除の手続きを行う」などのようなことは認められていないわけです。
このため、相続廃除をしたい相手がいる場合、夫本人の決断・手続きによって迅速に事を進めていく必要があります。
「夫の最後の願いを叶えたい」「遺産に関しては、夫の意向を尊重したい」と考える人もいるでしょう。
そのような場合は、上記の手続きのどれが選択できるかを一緒に考えていくようにしてください。