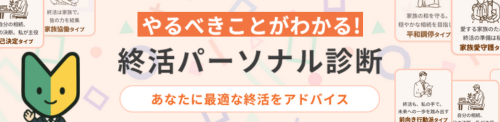遺産の相続のときにほぼ必ず話題に上るものが「相続税」です。しかし実は相続税は、「絶対に発生するもの」ではありません。さまざまな控除や特例があり、それから逸脱したものに対してのみしか相続税は課せられません。
そのため、「相続税がかかったケース」を「相続税がかからなかったケース」と比較すると、その割合は1:9程度になります。つまり、10ケースのうちの1ケース程度の相続にしか、相続税は発生していないのです。これは年によって多少異なりますが、基本的にはこの割合から大きくはずれません。
今回は、多くの人を「相続税がかからないケース」にあてはめることになる「相続税の控除」について解説していきます。
基礎控除
「相続税の控除」を考えたときに、まず真っ先に挙げられるのが「基礎控除」です。これは非常に有名なので、名前を聞いたことがある人も多いのではないでしょうか。
基礎控除とは、「3000万円+(600万円×法定相続人)内の遺産にとどまった場合、相続税を収める必要はない」とする制度です。
たとえば、妻・子ども1・子ども2がいる場合、3000万円+600万円×3人=4800万円まででは非課税とされます。
なお、「遺されたのが子ども2人であり、遺産の総額が5000万円である」などのケースの場合は、3000万円+600万円×2人=4200万円までが非課税範囲となりますが、残りの800万円は相続税の対象となります。
基礎控除以外の控除
上で挙げた「基礎控除」は、相続税の控除制度としてもっとも有名なものですが、それ以外にも相続税を控除できる制度があります。それについて見ていきましょう。
贈与税額控除
生前に贈与を行う場合の税金に関わる制度として、「暦年贈与」と「相続時精算課税制度」があります。非常に簡単に言うと前者は「毎年110万円以内の贈与ならば贈与税はかからない」とするもので、後者は「2500万円以内の贈与ならば贈与税はかからない」とするものです(※後者の場合は「年齢」「関係性」によって制限を受けます)。
なお、どちらのケースであっても、制限となる金額を上回った分に関しては「贈与税」というかたちで税金が発生します。
相続時精算課税制度を選択したもの及び一定期間に行われた暦年贈与は相続財産に加算されます。この際、前もって支払っていた贈与税については相続税から差し引くことができます。これは税金を二重に取ることを防ぐための措置です。
配偶者控除
「配偶者控除」は非常に強力な制度です。
これは、
1. 配偶者の法定相続分
2. 1億6000万円
のいずれかの「高い方」の金額以下ならば、相続税を免除するというものです。1億6000万もの財産を持っている人は非常に少ないため、多くの場合、配偶者は相続税の加算対象外となります。
ただしこれはあくまで「法律上の配偶者」のみが使うことのできる制度であるため、内縁の配偶者の場合はこれを利用できません。
未成年者控除
「相続人のなかに未成年がいた場合、その未成年の相続税額から一部の金額を控除する」という制度を「未成年者控除」といいます。なお今まで「未成年」といえば20歳を指していましたが、2022年以降は18歳にこれが引き下げられました。この未成年者控除の金額は、「10万円×18歳になるまでの年数」と定められています。つまり10歳ならば80万円だということです。
なおこの未成年者控除は、未成年の教育費・養育費が必要であるという観点にのっとって制定されました。
障害者控除
「障がい者でない人に比べて、障がいを抱えている人は生活費の負担が大きい」ということから設定されたのが「障害者控除」です。これは、「相続人のなかに障がいを抱えた人がいる場合、その人が引き継ぐことになる財産のなかから、一定金額を相続税の対象から除く」とした制度です。
相続を受ける側が85歳以下の障がい者である場合に適用される制度であり、「10万円(障がいの種類や程度によっては20万円)×85歳になるまでの年数」の金額分が免除されます。
外国税額控除
比較的珍しいケースかもしれませんが、「亡くなった人の財産が、国外にある」ということもありえます。このような場合、その「財産がある国」で相続税が発生する可能性が十二分に考えられます。
国外で相続税が発生したにも関わらず、日本でさらに相続税がかかるとなると、相続した人が二重に課税されることになります。そのためこれを避けるために「外国税額控除」が設定されました。
これは、
1. 国外の国で納めた相続税に相当する金額
2. 日本の相続税額と国外の財産の評価額を掛け合わせ、それを該当相続人の相続財産の評価額合計で割った数字
のいずれか「少ない方」を控除すると定められています。
小規模宅地等の特例
「小規模宅地等の特例」とは、条件をクリアすれば土地にかかる相続税の評価額を最大80パーセントまで減額できる制度のことを指します。
これは土地の条件や引き継ぐ人などの立場によって適応されるかどうかが変わってくるものであり、「生前にその人がどこに住んでいたか」「土地の生前贈与の履行はあったかなかったか」などによっても適応できるかどうかが変わってきます。ただ、利用できれば非常に効果的な方法だといえます。
相次相続控除
「相次相続控除」とは、「相続が発生してから10年以内に、次の相続が発生した場合には、一定額の相続税を差し引くことができる」という制度です。たとえば、「2000年に祖母を亡くして、2004年に祖母の遺産を相続した父を亡くした」という状況のときに使えるものです。
この「相次相続控除」の考え方は、相続人の生活と財産を守るために生まれました。相続に関しては「基礎控除」という考え方はあるものの、相続税自体の税率は非常に高く、1000万円以下でも10パーセントです。そして相続財産が多くなればなるほど税率は上がっていき、最大で55パーセントにもなります(※相続税が15パーセント以上になる場合は、控除あり)。
このため、短いスパンで相続税が発生することによる経済的な負担から、相続した人を守ろう」として、相次相続控除の制度が作られたわけです。
相次相続控除は、
1. 法定相続人であること
2. 前回の相続開始から10年以内に、次の相続が発生したケースであること
3. 前回の相続において、相続税が発生していること
を条件とします。
詳しい計算式についてはここでは取り上げませんが、「1回目の相続と2回目の相続のスパンが短ければ短いほど、控除される金額は大きくなる」と考えておきましょう。なおこの相次相続控除は、「10年間に、2回だけではなく3回相続があった」などのようなケースでも使えます(この場合、3回目の相続は2回目の相続税を対象とします)。
死亡保険の非課税対象
「遺された家族のために、生命保険に入っている」という人は、そう少なくはないのではないでしょうか。この「死亡保険」は、もともと「遺された家族の生活を守るためのものである」という考え方に基づいて運用されています。そのため、一定額ならば非課税対象として扱われます。
死亡保険の非課税対象額には、明確な計算式があります。それが、「法定相続人の数×500万円」です。つまり、夫・子ども1・子ども2の場合は、法定相続人の数3人×500円となり、1500万円までの死亡保険は非課税となります。配偶者がすでに死亡(あるいは離縁)していて、子どもが4人の場合は、法定相続人の数4人×500万円となり、2000万円までの死亡保険が非課税となります。
なお現在は、「たとえ入籍はしていなくても、いわゆる「内縁の妻」の状態であるならば、生命保険の受取人にできる」としているプランもないわけではありません。しかし上で述べた「死亡保険の非課税対象額」を計算するときに使われるのは、あくまで「法定相続人の数」であるため、内縁の妻の場合はここに含まれません。
ここまでいくつか「相続税の控除」について取り上げてきましたが、これが実際に利用できるかどうかは、個々の事例によります。 実際に相続が発生した場合は、専門家の意見を仰ぎましょう。また、相続税対策を考える場合も、一度専門家に相談した方が賢明です。