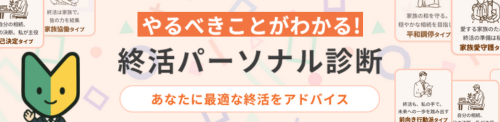民法と不動産登記法が2021年4月に改正され、2023年4月1日から改正民法が施行されることになりました。改正民法によって、相続した際の遺産分割ルールが変わります。
しかし多くの人は遺産分割ルールがどのように変わったのかよくわからないという人も多いでしょう。本記事では、2023年4月から適用された遺産分割ルールの変更点についてご紹介します。
「遺産分割」とは
祖父母や父母などが亡くなることで相続が発生します。相続が発生すると残された家族で遺産分割を行うことになります。遺産分割とは、残された相続人との間で、相続財産を分ける手続きのことです。
遺産分割は、民法で定められた法定相続分を基本としつつ、個別の事情などを考慮して分けられます。相続人同士で協議して決める遺産分割協議が一般的であり、もし遺産分割協議で話がまとまらず、相続人同士で揉めることになれば調停や審判といった法的手続で決まることもあります。
遺産分割自体は、期限の制限がありません。また長期間放置していたとしても遺産分割を希望する相続人に不利益があるわけではないため、そのままにしていることも多いです。しかし遺産分割を長期間放置することで、生前贈与や寄与分に関する書類などをなくしてしまったり、相続人の記憶も薄れてしまったりすることで具体的な相続分を計算する上で支障が出ることもあります。
そういった事情から民法が改正され、特別受益や寄与分がある場合、10年以内に遺産分割しなければ、法定相続分による相続になるといった制限が設けられました。
遺産分割の基本的なルール
遺産分割は相続人に「特別受益」と「寄与分」があれば、それらを考慮して分けられます。
特別受益とは、相続人の中で亡くなった人から生前贈与や遺贈によって特別の利益を受けた人のことです。例えば、亡くなった人の子どもの配偶者が生前に献身的に介護などを行っていた場合、その配偶者は法定相続人ではないため、相続財産を受け取れません。しかし生前のうちに贈与を受けていたり、相続財産を受け取れるように遺言したりします。
寄与分とは、家族の中で亡くなった人の財産の維持や増加に貢献した人のことです。例えば、亡くなった人の事業を無給で手伝ったり、献身的に介護を担ったりした場合、遺産分割協議の際に相続人同士で話し合って寄与分の金額を上乗せして相続します。
相続が発生したものの、兄弟仲が良いこともあって遺産分割しないままになっていたり、祖父母が亡くなった際の遺産分割を親世代がそのままにしていたりすると遺産分割が進まないことがあります。
遺産分割ルールの変更で損する人
遺産分割に期限はないものの、改正民法によって相続開始から10年を経過した場合、「具体的相続分ではなく法定相続分」によることが定められました。つまり「特別受益」や「寄与分」があったとしても法定相続分による遺産分割となるため、受け取れない場合や相続財産が減ってしまうことがあります。
ただし例外として2つあります。1つは、10年経過する前に相続人が家庭裁判所に遺産分割請求した場合です。もう1つが、10年の期間満了前の6ヶ月以内に相続人に遺産分割請求できないやむを得ない理由があった場合、その理由がなくなった時から6ヶ月経過する前に、その相続人が家庭裁判所に対して遺産分割請求を行ったときとなります。
また10年経過した後、法定相続分などの分割を求めることができるにもかかわらず、相続人全員が特別受益や寄与分を含めた「具体的相続分」によって遺産分割することを合意していれば、「具体的相続分」による遺産分割が可能です。
特別受益の場合
特別受益がある場合となくなった場合で計算をしてみましょう。父が亡くなって、相続人は妻、長男、長女の3人が、相続財産である預金4,000万円を遺産分割します。なお長男は結婚などのために500万円の贈与を受けています。特別受益を受けた場合を計算すると次のようになります。
| 相続人 | 法定相続分 | 遺産分割した財産 (特別受益あり) |
| 妻 | 2分の1 | 2,250万円 |
| 長男 | 4分の1 | 625万円 |
| 長女 | 4分の1 | 1,125万円 |
しかし特別受益がなくなると次のようになります。
| 相続人 | 法定相続分 | 遺産分割した財産 (特別受益なし) |
| 妻 | 2分の1 | 2,000万円 |
| 長男 | 4分の1 | 1,000万円 |
| 長女 | 4分の1 | 1,000万円 |
相続が発生してから10年が経ってしまうと長男が受けていた特別受益がなくなり、法定相続分で計算されてしまいます。
寄与分の場合
寄与分がある場合となくなった場合も計算してみましょう。父が亡くなって、相続人は妻、長男、次男の3人が、相続財産である預金4,000万円を遺産分割します。なお次男は父親の介護をしていたため寄与分として400万円が認められました。寄与分を受けた場合を計算すると次のようになります。
| 相続人 | 法定相続分 | 遺産分割した財産 (寄与分あり) |
| 妻 | 2分の1 | 1,800万円 |
| 長男 | 4分の1 | 900万円 |
| 次男 | 4分の1 | 1,300万円 |
しかし特別受益がなくなると次のようになります。
| 相続人 | 法定相続分 | 遺産分割した財産 (寄与分なし) |
| 妻 | 2分の1 | 2,000万円 |
| 長男 | 4分の1 | 1,000万円 |
| 次男 | 4分の1 | 1,000万円 |
相続が発生してから10年が経ってしまうと次男の寄与分がなくなるため、次男の受け取れる金額が減り、相対的に妻と長男の相続財産が増えています。
損をしないために何をしたらいいか
2023年4月から始まった改正民法によって、相続が発生してから10年を過ぎてしまうと、特別受益や寄与分を主張したとしても考慮されなくなってしまいます。そのため法定相続分で遺産分割されます。
特別受益や寄与分がある場合、本来得られる相続財産が少なくなってしまうため、もし主張したいと思っている相続人は、10年以内に遺産分割する必要があります。相続が発生してから、なるべく時間を空けずに遺産分割協議を始めるようにすることが大切です。
なお2023年4月1日よりも前に発生した相続の場合、猶予期間があります。原則として2023年4月1日から5年の猶予期間があり、もし相続が発生してから10年の経過時期が2023年4月1日から5年より後の場合、相続開始から10年以内となります。
民法が改正されて施行されたばかりではあるものの、もし特別受益や寄与分があって主張したいと思っている場合、早めに遺産分割するようにしましょう。